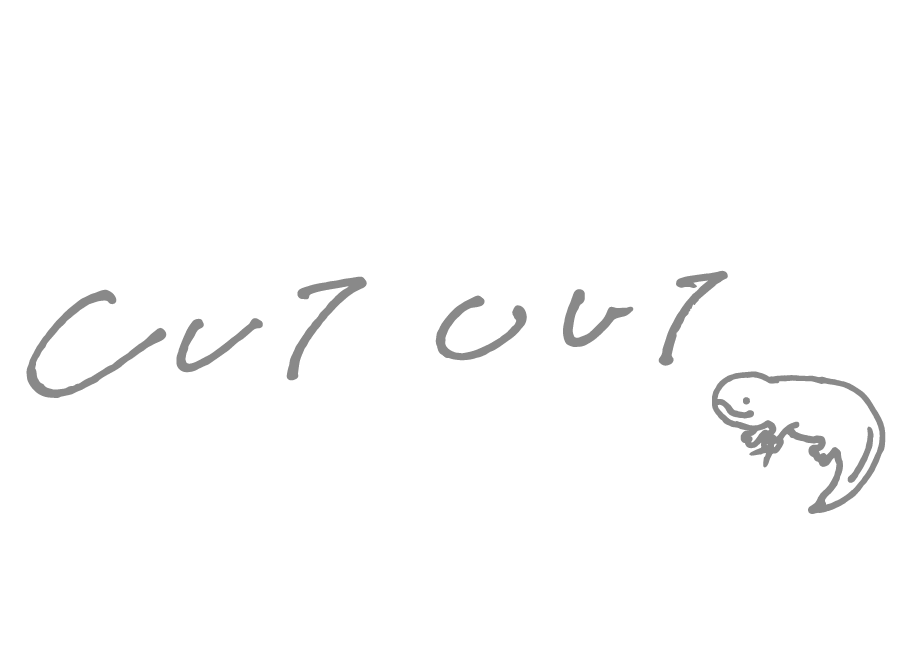いつか父の仕事場を撮りに行きたいと思っていた。
偶然空いた週末をめがけ、思い出したように父に声を掛けた。


自転車を走らせ30分ほど、家で手持ち無沙汰になると
ひとりで遊びに来ていた。
幼い自分にとって、ここは巨大な図画工作室だった。


機械がけたたましいエンジン音とともに
銀の切り子と火花を散らしている。
巻き込まれたら指が飛ぶらしい。
そうと分かりつつ父は軍手ひとつでそれを握りしめる。
まるで闘牛の角を掴むような手つきで。
蛍光灯が照らす腕の筋を見て、こんなに逞しい
腕だったかと思う。自分より小さいはずの父を
下から見上げているような感覚になる。


手に取る設計書にはφに続く寸法と製図が示されている。
子どものころ、リビングの隅で図面を書き込む姿をよく見ていたことを思い出した。
大人になり、仕事とは何だと堅い話を交わすようになった。
職種も何も違うけれど、姿勢や考え方に共感する瞬間があって
少し分かりあったような気持ちになる。
ただ同時に、己のことだけに必死な自分と家族の生活を支える
父の矜持を同じ秤に乗せるのはおこがましいぞ、とも思う。


金属が削られるたび散らかる切り子も、削られ出来た
ボルトも平等に美しい。
銀色とも鈍色とも喩えられないこの色がいい。
いまここで撮影することは、家族の記録でも、まして孝行でも何でもない。
廃材で椅子を組み上げた子供の頃と同じ気持ちになりながら
ただ夢中にシャッターを切っていた。