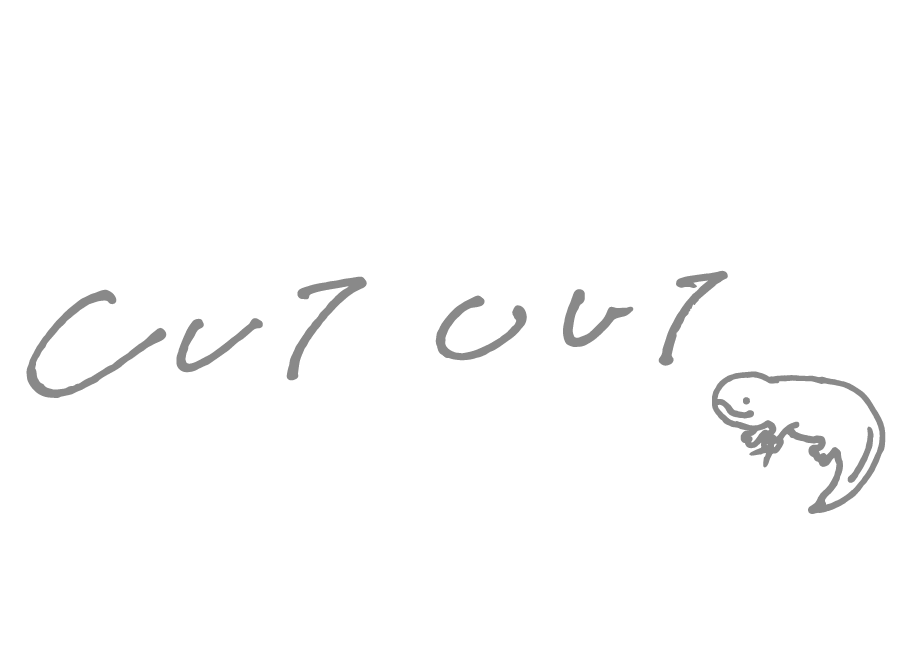人の手によって象られたかたちに感じる温もり。
釉薬の彩りや刻まれた模様も、一つとして同じではない特別なもの。
そんな"うつわ"の魅力とルーツを紹介します。
波佐見焼(長崎県) | 龍庵窯
美しい白磁と繊細な絵付が魅力の波佐見焼。
人口のおよそ2〜3割が陶磁器生産に携わると言われる波佐見町では「分業制」によって各所が特化した生産を行うことで高品質と大量生産の両立を実現しました。
実は2,000年ころまで県境の名産・有田焼として作られていましたが、波佐見の名を冠し数々の名窯を有する今では日用和食器において全国3位の出荷量を誇る産地へと成長を遂げました。
手びねり小皿



ぐいっと捻り上げたような四隅の端と、美しい緑の貫入が印象的な小皿。
割れ模様の下には、金箔をひと筋あしらった花柄がちらりと覗き上品さを添えます。
普段の料理は勿論のこと、来客の折にお茶菓子を乗せて出したくなる特別感あふれる1枚。
丹波立杭焼(兵庫県)| 俊彦窯
およそ800年以上の歴史を持ち、日本六古窯の一つとして名高い丹波焼。中でも主要な窯が集まる立杭地区において、俊彦窯はその個性と使いやすさから根強い人気を誇ります。
土そのものの質感を感じさせるような古風さと洋のディテールを見事に融合させ、皿類やマグカップを代表に広く愛されるテーブルウェアを生産してきました。
時代のニーズを汲みながら発展してきた丹波焼ならではの魅力を体現する名窯です。
七寸皿



ずっしりと厚口で無骨な造形に、素地を削り出して刻まれる鎬のモダンな装飾が入った七寸皿。
糠釉により纏った白鼠色がほのかなあたたかみを感じさせます。横から見ると稜線が大きく波立っているのが分かります。
和食のみならずカレーやパスタ等、個性派でありながら様々な料理ジャンルに使える汎用性が魅力。
信楽焼(滋賀県) | 古谷製陶所
「たぬきの置物」で広く知られる信楽焼。その起源となった陶土は、琵琶湖の原型となる古代湖の湖底に堆積した「古琵琶湖層」に由来し、これは粘土質で耐火性に優れることから焼き物に適していました。
以来京都を中心に供給を広げ、現在に至るまで大きく発展していった歴史があります。
1970年に古谷信男氏が立ち上げた「古谷製陶所」は、暮らしに寄り添うことをテーマにさまざまな器を提案。ざらりとした手触りと、優しさあふれる粉引きの「白」が食卓に温もりを添えてくれます。
豆皿



素朴でなめらかなかたちが何とも愛らしい豆皿。
表面をなぞると小さな黒の鉄点やピンホールがあり、土の細やかな凹凸が伝わります。
マットでかつ肌色がかった白のトーンはどんな食器とあわせてもよく馴染みます。窪みが浅く付けられており漬物や佃煮をはじめたれ皿としても最適。
お気に入りのうつわで食べる料理は、いつもより少し美味しくて嬉しい。
焼物の奥深い魅力の片鱗に触れるきっかけになれば幸いです。